最近は、だいたいの人は携帯電話を持っていて、使われることの少なくなった公衆電話。何かの必要があって、「さて公衆電話は?」と思うと、なかなか見つからなかったりする。

公衆電話はもうすこし古くからあるが「電話ボックス」というものができたのは1950年代。今のようなガラス張りではなくて、なんといったらいいのだろう。大きさは似たようなものだが、窓のついた箱型の。
その、わりあい早い時期の例はこういう作品。1954年の歌集。
夕さればやさしくベルの鳴らさるる電話ボックスはあかしやの蔭/中城ふみ子『乳房喪失』
昔は、電話ボックスの中に書いてある番号が、そのまま電話番号で、電話ボックスに電話をかけるということも難しくはなかったらしい。
その後の時代も、何らかの方法で電話ボックスに電話をかけるというような話はあった。犯罪がらみで「どこそこの電話ボックスで指示を待て」とか、ふたつの公衆電話の受話器をつなぐようなトリックなど〈探偵もの〉でよく使われたりもした。
とはいえ、誰もいない電話ボックスで、電話が鳴ったらびっくりする。「あかしやの蔭」とあるが、なにか「あやかし」が出てきそうだ。
仕事終へし眼上ぐれば部屋隅の電話ボックス灯りてゐぬ/古賀泰子『溝河の四季』
ペンキ剥げし電話ボックス出でしより憑かれし如く街を行きゆく/西岡敦子「沈める鍵」(塔作品集Ⅱ)
これらの作品も1950年代の前半。
古賀作品は「ボックス」というが、これはちょっと違うものだろう。
学校の職員室に置かれた公衆電話。
西岡作品は、この段階でペンキが剥げているということに、ちょっと驚く。できてまだ数年だが、本体の材質とかペンキとか、そのくらいのものだったのか。
街筋に流るる霧は二十メートル先の電話ボックスの灯も隠しゆく/高安国世『北極飛行』
1960年の歌集。
これも「電話ボックス」が出て来る作品としては早いが、日本のことではない。在外研究で滞在したドイツの町角のこと。


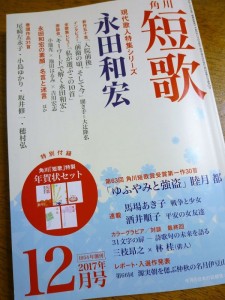







![IMG_1770[1]](https://toutankakai.com/cms/wp-content/uploads/2017/11/IMG_17701-e1510465891241-225x300.jpg)



