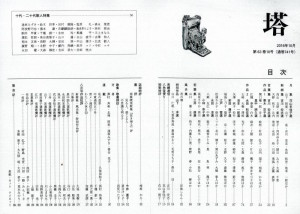数年前から能面を打つ教室に通っています。家でもすこしずつ彫ったり塗ったりをしているので、部屋のなかはいつも檜や漆の匂いでいっぱい。だいたいひとつ完成するのに半年くらいはかかります。質・数ともにまだまだですが、わたしが打った能面を短歌とともに紹介します。近代短歌にも現代短歌にも能楽を題材にした歌はたくさんありますが、なかでも能面に光を当てた歌、なかなか面白いのです。

これは「痩女」(やせおんな)という、恋のために地獄に落ちた女性の亡霊です。年老いて見えるかもしれませんが、実はまだ若い。若いけれど、地獄の苦しみを見てしまったためにこんな表情になりました。頬骨にまとわりつく皮膚のエロス。本面(現代の能面作家は基本的には、過去のすごい面打ちが打った面をお手本にします)は氷見(ひみ)という室町時代の能登の僧侶のもの。
馬場あき子の第九歌集『葡萄唐草』には「氷見」という連作がありますが、この氷見というひとは死者の顔をモデルにしつつ「痩女」や「痩男」など死霊的な面ばかり残した伝説的な能面師なのです。連作には「氷見といふ男ありぬ。痩せたる死者の面のみを打ちて死にき。会ひたかりけり」という前書きの後、
氷見痩せて生きて面打つ荒冬のふぶきの嵩を浄くせし灯よ
一削ぎに氷見がけづりし痩面の頬を寒しと鳴けきりぎりす
といった歌が並びます。私も氷見に会ってみたかった。
土岐善麿にも氷見についての連作があります。
氷見に住み氷見宗忠と銘打ちて残せし面はいくつありしか
研ぎすます一挺の鑿灯のもとに雪のひかりの沁み透りけむ

これは「泥眼」(でいがん)といって、例えば「葵上」の六条御息所などに使われる女面です。恨みがましく悔しそうなくちもとの造形や両眼に入った金泥(この写真ではわかりにくいですが、角度によってきらっと光る)が特徴で、眼が金色に光るのは、生きながらにしてすでに異形のものになりかけているしるしだそうです。
山中智恵子の『喝食天』に「面百詠」という連作があり、泥眼も詠まれています。
うつしよを過ぎゆきしもの増の面きみ泥眼を打つことなかれ
泥眼を打てば終りぞこの世界尽きなむときに必ず生(あ)れむ

これは「宝増」(ほうぞう)といって高貴でうつくしい女面「増女」(ぞうおんな)の一種なのですが、まだ制作途中です。下塗りの段階ではこんな感じで、何も色彩がはいっていない顔がかえって怖いかも。